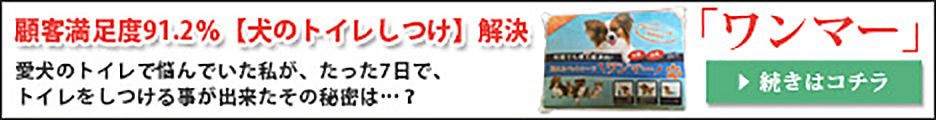愛犬が下痢で苦しんでいる?もしかして腸リンパ管拡張症かも?
- えふ子
- 2024年5月29日
- 読了時間: 4分

愛犬が慢性的な下痢や体重減少に悩んでいる飼い主さん、もしかして腸リンパ管拡張症という病気が原因かもしれません。
今回は、犬の腸リンパ管拡張症について、原因、症状、治療、なりやすい犬種、低アルブミン血症との関係など、飼い主さんが知っておきたいポイントを10個にまとめました。
愛犬の健康を守るために、ぜひ参考にしてください。
1. 腸リンパ管拡張症とは?
腸リンパ管拡張症は、腸のリンパ管が拡張したり破れたりすることで、リンパ液が腸管内に漏れ出し、低タンパク血症やむくみなどの症状が現れる病気です。
1.1 リンパ管とは?
リンパ管は、体中の余分な水分や老廃物を回収し、免疫細胞を運ぶ役割を担う管です。腸のリンパ管も同様に、腸管内に入った水分や栄養素を吸収し、血液中に運ぶ役割を担っています。
1.2 腸リンパ管拡張症が起こるメカニズム
腸リンパ管拡張症は、先天的な要因や後天的な要因によって、腸のリンパ管が弱くなり、拡張したり破れたりすることで起こります。
先天性: 遺伝的な要因でリンパ管が弱く、拡張しやすい
後天性: 腸炎、リンパ腫、寄生虫感染などの病気によってリンパ管がダメージを受ける
1.3 腸リンパ管拡張症の病態
腸のリンパ管が拡張したり破れたりすると、リンパ液が腸管内に漏れ出し、以下のような病態が起こります。
低タンパク血症: リンパ液はタンパク質を豊富に含んでいるため、腸管内に漏れ出すと、血液中のタンパク質量が低下します。タンパク質は、体の組織や臓器を構成する重要な役割を担っているため、低タンパク血症になると、様々な症状が現れます。
むくみ: リンパ液は体内の余分な水分を回収する役割を担っているため、腸管内に漏れ出すと、体内に水分が蓄積し、むくみが起こります。
消化不良: リンパ液が腸管内に漏れ出すと、腸の正常な働きが阻害され、消化不良が起こります。
1.4 低アルブミン血症との関係
リンパ液には、血液中のタンパク質量の約半分を占めるアルブミンが含まれています。
アルブミンは、体内の水分を保持したり、栄養素を運んだり、免疫機能を維持したりする重要な役割を担っています。
腸リンパ管拡張症になると、リンパ液が腸管内に漏れ出すため、血液中のアルブミン量が低下し、低アルブミン血症を引き起こします。
低アルブミン血症になると、むくみ、倦怠感、食欲不振、下痢などの症状が現れます。
症状
腸リンパ管拡張症の主な症状は以下の通りです。
慢性的な下痢
体重減少
食欲不振
嘔吐
脱水症状
腹水・胸水貯留
むくみ
低アルブミン血症による症状(むくみ、倦怠感、食欲不振、下痢など)
治療
腸リンパ管拡張症の根本的な治療法は確立されていませんが、症状を抑制し、犬の生活の質を向上させるための対症療法が行われます。
食事療法: タンパク質や脂肪を制限した食事を与える
薬物療法: 下痢止め、利尿剤、抗炎症薬などの薬を投与する
輸血: 低タンパク血症が著しい場合は輸血を行う
予後
腸リンパ管拡張症は完治が難しい病気ですが、適切な治療と管理によって、症状をコントロールし、犬の寿命を延ばすことは可能です。
なりやすい犬種
腸リンパ管拡張症は、どの犬種でも発症する可能性がありますが、特に以下の犬種で発症しやすい傾向があります。
ヨークシャテリア
マルチーズ
ミニチュアダックスフンド
チワワ
パピヨン
予防
腸リンパ管拡張症の予防には、以下の点に注意することが大切です。
バランスのとれた食事を与える
適度な運動をさせる
定期的な健康診断を受ける 腸リンパ管拡張症は早期発見・早期治療が重要です。そのため、愛犬を定期的に動物病院に連れて行き、健康診断を受けることが大切です。 健康診断では、血液検査や便検査などを行い、腸リンパ管拡張症の兆候がないかどうかを確認します。
ストレスを溜めない ストレスは、腸の働きを低下させ、腸リンパ管拡張症を発症しやすくする可能性があります。 愛犬がストレスを感じないように、以下のような点に注意しましょう。
十分な運動をさせる
規則正しい生活を送る
遊んであげる時間を増やす
スキンシップをたくさん取る
肥満を予防する 肥満は、腸に負担をかけ、腸リンパ管拡張症を発症しやすくする可能性があります。 愛犬が肥満にならないように、適切な食事を与え、適度な運動をさせることが大切です。
獣医師に相談する 愛犬に以下のような症状が見られた場合は、すぐに獣医師に相談しましょう。 獣医師は、症状や検査結果に基づいて、適切な治療法を提案します。
慢性的な下痢
体重減少
食欲不振
嘔吐
脱水症状
腹水・胸水貯留
むくみ
まとめ
腸リンパ管拡張症は完治が難しい病気ですが、適切な予防と治療によって、症状をコントロールし、犬の寿命を延ばすことは可能です。
愛犬の健康を守るために、この記事で紹介した予防法を参考に、できることから実践していきましょう。
※この記事はあくまでも情報提供を目的としたものであり、獣医師の診断や治療に代わるものではありません。愛犬の健康に不安がある場合は、必ず獣医師に相談してください。