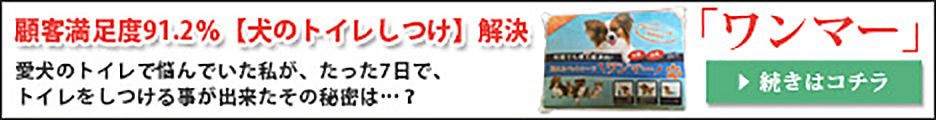愛犬との未来を守る選択:去勢・避妊手術の疑問を解決!!
- えふ子
- 2024年9月11日
- 読了時間: 8分

愛犬の去勢・避妊手術、あなたは考えていますか?
ペットを家族として迎え入れることは、大きな喜びと責任を伴います。
その責任の一つとして、近年注目されているのが「去勢・避妊手術」です。
これは、犬の繁殖能力をなくす手術ですが、健康面や行動面への影響など、様々なメリットとデメリットがあります。
この記事では、去勢・避妊手術に関する基本的な情報から、飼い主さんが抱える疑問、そして手術を受けるかどうかの判断材料となるポイントまで、獣医師の監修のもと、詳しく解説していきます。
目次
去勢・避妊手術とは?
去勢手術:オス犬の場合
避妊手術:メス犬の場合
手術のメリット:愛犬の健康と幸せを守るために
望まない繁殖の防止:不幸な命を増やさない
病気の予防:将来的なリスクを軽減
問題行動の抑制:ストレスを減らし、穏やかに
手術のデメリット:知っておきたいリスクと変化
繁殖能力の喪失:子犬を望む場合は慎重に
麻酔のリスク:手術には必ずリスクが伴う
体質の変化:太りやすさや性格の変化も
手術の時期:最適なタイミングはいつ?
去勢・避妊手術に関する疑問:費用や術後のケアなど
費用はどれくらい?:病院や地域によって異なる
手術後のケア:傷口管理と生活の変化
迷っている方へ:獣医師への相談を
まとめ:愛犬にとって最善の選択を
去勢・避妊手術とは?
去勢手術:オス犬の場合
去勢手術は、オス犬の精巣を摘出する手術です。これにより、精子の生産が停止し、繁殖能力がなくなります。また、男性ホルモンの分泌も減少するため、性衝動や攻撃性、マーキングなどの問題行動が軽減される効果も期待できます。
避妊手術:メス犬の場合
避妊手術は、メス犬の子宮と卵巣を摘出する手術です。これにより、卵子の生産が停止し、繁殖能力がなくなります。また、女性ホルモンの分泌も減少するため、発情期の出血やそれに伴うストレス、乳腺腫瘍や子宮蓄膿症などの病気のリスクを軽減する効果も期待できます。
手術のメリット:愛犬の健康と幸せを守るために
望まない繁殖の防止:不幸な命を増やさない
去勢・避妊手術の最大のメリットは、望まない繁殖を防ぐことです。日本では、毎年多くの犬や猫が殺処分されています。その原因の一つが、無計画な繁殖による飼育放棄です。去勢・避妊手術を行うことで、このような不幸な命を増やさないことに繋がります。
病気の予防:将来的なリスクを軽減
去勢・避妊手術は、様々な病気の予防にも繋がります。
オス犬
精巣腫瘍、前立腺肥大症、会陰ヘルニアなどのリスクを軽減
メス犬
乳腺腫瘍、子宮蓄膿症、卵巣腫瘍などのリスクを軽減
これらの病気は、高齢になった犬に多く見られ、治療には手術や長期の投薬が必要となる場合があります。去勢・避妊手術は、これらの病気のリスクを大幅に減らし、愛犬の健康寿命を延ばすことに繋がります。
問題行動の抑制:ストレスを減らし、穏やかに
去勢・避妊手術は、性ホルモンの分泌を抑制するため、以下のような問題行動の軽減に繋がります。
オス犬
マーキング、マウンティング、攻撃性、脱走などの抑制
メス犬
発情期の出血、鳴き声、落ち着きのなさなどの抑制
これらの問題行動は、犬自身にとってもストレスとなります。去勢・避妊手術は、これらのストレスを軽減し、犬がより穏やかに過ごせるようにサポートします。
手術のデメリット:知っておきたいリスクと変化
去勢・避妊手術は、愛犬の健康と幸せを守るための選択肢の一つですが、同時にいくつかのデメリットやリスクも存在します。手術を受けるかどうかを判断する前に、これらのデメリットについても理解しておくことが重要です。
繁殖能力の喪失:子犬を望む場合は慎重に
去勢・避妊手術は、犬の繁殖能力を永久になくす手術です。将来、愛犬の子犬を望む場合は、手術を受ける前に慎重に検討する必要があります。
麻酔のリスク:手術には必ずリスクが伴う
去勢・避妊手術は、全身麻酔下で行われるため、麻酔によるリスクが伴います。高齢の犬や持病のある犬は、麻酔のリスクが高くなる可能性があります。手術前に、獣医師としっかりと相談し、愛犬の健康状態を考慮した上で手術を受けるかどうかを判断しましょう。
体質の変化:太りやすさや性格の変化も
去勢・避妊手術は、ホルモンバランスの変化を引き起こすため、体質や性格に変化が生じる可能性があります。
太りやすくなる: 性ホルモンの分泌が減少することで、基礎代謝が低下し、太りやすくなることがあります。手術後は、食事量や運動量を調整し、適切な体重管理を行うことが重要です。
性格が変化する可能性: 去勢手術を受けたオス犬は、攻撃性やマーキング行動が軽減される一方で、やや落ち着きがなくなり、活動的になる場合があります。避妊手術を受けたメス犬は、穏やかになる一方で、依存心が強くなる場合があります。これらの変化は、すべての犬に当てはまるわけではありませんが、可能性があることを理解しておきましょう。
尿失禁: 避妊手術を受けたメス犬の一部に、尿失禁が起こる可能性があります。これは、女性ホルモンの減少によって尿道括約筋が弱まるためです。特に、大型犬や高齢犬での発症率が高いと言われています。
手術の時期:最適なタイミングはいつ?
去勢・避妊手術の最適な時期は、犬種や個体差、そして手術の目的によって異なります。
一般的な目安
オス犬:生後6ヶ月~1歳頃
メス犬:初回発情前(生後6ヶ月~1歳頃)
早期手術のメリット
望まない妊娠のリスクを早期に回避できる
乳腺腫瘍などの生殖器関連の病気のリスクを大幅に軽減できる
問題行動の予防に繋がる
早期手術のデメリット
成長過程でのホルモンバランスの変化が、骨格形成や性格形成に影響を与える可能性がある
一部の犬種では、早期手術が特定の病気のリスクを高める可能性があるという報告もある
遅らせる場合の注意点
メス犬は、初回発情後に避妊手術を行うと、乳腺腫瘍の予防効果が低くなる
高齢になるほど、麻酔のリスクが高まる
手術の時期については、獣医師とよく相談し、愛犬にとって最適なタイミングを選びましょう。
去勢・避妊手術に関する疑問:費用や術後のケアなど
費用はどれくらい?:病院や地域によって異なる
去勢・避妊手術の費用は、動物病院や地域、犬の大きさや年齢、手術内容などによって異なります。
一般的な費用相場
去勢手術:1万円~5万円程度
避妊手術:2万円~8万円程度
費用に含まれるもの
手術費用、麻酔費用、入院費用、薬代など
追加費用
術前の検査費用、術後のケア用品費用、合併症が生じた場合の治療費など
手術を受ける前に、複数の動物病院に見積もりを取り、費用やサービス内容を比較検討することをおすすめします。
手術後のケア:傷口管理と生活の変化
手術後は、傷口のケアや安静、食事管理、運動制限など、適切なケアが必要です。
傷口のケア: 毎日傷口の状態を確認し、清潔に保ちましょう。エリザベスカラーを装着して、犬が傷口を舐めないように注意が必要です。
安静: 術後は、激しい運動やジャンプを避け、安静に過ごさせましょう。
食事管理: 術後は、消化の良い食事を与え、太りすぎないように注意しましょう。
運動制限: 術後しばらくは、散歩の時間を短くしたり、激しい運動を避けたりする必要があります。獣医師の指示に従いましょう。
術後のケアについては、獣医師から詳しく説明を受けることができます。指示をよく守り、愛犬がスムーズに回復できるようにサポートしましょう。
迷っている方へ:獣医師への相談を
去勢・避妊手術を受けるかどうか迷っている場合は、まずは獣医師に相談してみましょう。愛犬の健康状態や性格、ライフスタイルなどを考慮した上で、メリットとデメリットを丁寧に説明してくれます。また、手術を受ける場合の注意点や術後のケアについても、詳しく教えてくれるでしょう。
望まない繁殖を防ぐ:社会問題への貢献
愛犬の去勢・避妊手術は、個々の犬の健康を守るだけでなく、社会全体の課題解決にも貢献します。
日本では、毎年多くの野良犬や野良猫が保護され、その多くが殺処分されています。これは、無計画な繁殖や飼育放棄が主な原因です。去勢・避妊手術を行うことで、望まない繁殖を防ぎ、殺処分される動物の数を減らすことに繋がります。
地域社会への影響
望まない繁殖は、野良犬や野良猫の増加だけでなく、地域社会にも様々な問題を引き起こします。例えば、
糞尿被害: 野良犬や野良猫による糞尿被害は、衛生面や景観面で問題となります。
騒音被害: 野良犬や野良猫の鳴き声やケンカは、近隣住民にとって騒音となります。
交通事故: 野良犬や野良猫が道路に飛び出し、交通事故を引き起こす可能性があります。
感染症の蔓延: 野良犬や野良猫は、狂犬病などの感染症を媒介する可能性があります。
去勢・避妊手術は、これらの問題を未然に防ぎ、地域社会の安全と安心を守ることに繋がります。
まとめ:愛犬にとって最善の選択を
犬の去勢・避妊手術は、メリットとデメリットを比較検討し、愛犬にとって最善の選択をすることが重要です。
手術を受けることで、望まない繁殖を防ぎ、病気のリスクを軽減し、問題行動を抑制するなどのメリットが得られます。
一方で、繁殖能力の喪失や麻酔のリスク、体質の変化などのデメリットも存在します。
手術を受けるかどうか迷っている場合は、まずは獣医師に相談してみましょう。
愛犬の健康状態や性格、ライフスタイルなどを考慮した上で、最適なアドバイスを提供してくれます。
最終的な決断は飼い主自身が行う必要がありますが、この記事がその判断の一助となれば幸いです。
愛犬の健康と幸せを願い、責任ある飼い主として、去勢・避妊手術についてしっかりと考えてみましょう。