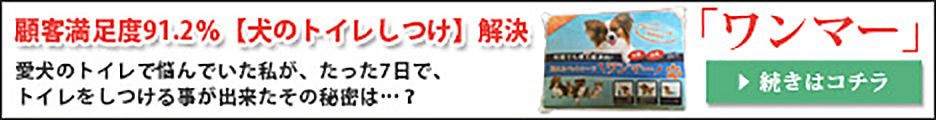愛犬を守ろう!10種混合ワクチンで予防できる病気と費用、接種の疑問を解説【犬 ワクチン】
- えふ子
- 2024年7月19日
- 読了時間: 4分
愛犬と安心して暮らすためには、感染症予防が欠かせません。
その中でも、10種混合ワクチンは、愛犬を守るための重要な手段の一つです。
「10種混合ワクチンって何?」「どんな病気から守ってくれるの?」「接種する際の注意点は?」など、疑問を持つ飼い主さんも多いのではないでしょうか?
この記事では、犬の10種混合ワクチンについて、飼い主さんが知っておくべき基本的な情報をまとめました。
ワクチンの種類や費用、接種スケジュール、注意点などを分かりやすく解説しますので、ぜひ最後まで読んで、愛犬の健康管理に役立ててください。
10種混合ワクチンとは?
10種混合ワクチンは、一度の接種で10種類の感染症から愛犬を守ることができるワクチンです。子犬の頃から定期的に接種することで、様々な病気のリスクを減らすことができます。
具体的には、以下の10種類の感染症を予防します。
ジステンパー: 発熱、咳、鼻水、嘔吐、下痢、神経症状などを引き起こし、重症化すると命に関わることもあります。
犬アデノウイルス感染症(2型): 肝炎を引き起こし、黄疸、腹水、食欲不振などの症状が現れます。
犬パルボウイルス感染症: 子犬に多く見られ、激しい嘔吐、下痢、脱水症状を引き起こし、致死率も高い感染症です。
犬伝染性肝炎: 肝臓に炎症を起こし、発熱、黄疸、腹痛などの症状が現れます。
犬パラインフルエンザ: 咳、鼻水、発熱などの呼吸器症状を引き起こします。
犬コロナウイルス感染症: 下痢や嘔吐を引き起こし、子犬や老犬では重症化することもあります。
犬レプトスピラ病: 発熱、黄疸、嘔吐、下痢、腎不全などを引き起こし、人にも感染する可能性があります。(2つの型を予防)
ケンネルコフ: 咳、鼻水、発熱などの呼吸器症状を引き起こし、集団感染しやすい感染症です。(2つの型を予防)
これらの感染症は、愛犬の生活環境や年齢によって感染リスクが異なります。
獣医さんと相談し、愛犬に最適なワクチンを選択しましょう。
10種混合ワクチンと5種混合ワクチンの違いは?
犬の混合ワクチンには、5種混合ワクチンと10種混合ワクチンの2種類があります。
5種混合ワクチンは、ジステンパー、犬アデノウイルス感染症(2型)、犬パルボウイルス感染症、犬伝染性肝炎、犬パラインフルエンザの5種類の感染症を予防します。
一方、10種混合ワクチンは、5種混合ワクチンの予防対象に加えて、犬コロナウイルス感染症、犬レプトスピラ病(2つの型)、ケンネルコフ(2つの型)も予防します。
愛犬の生活環境やリスクに応じて、どちらのワクチンを接種するか獣医さんと相談して決めましょう。
10種混合ワクチンの接種スケジュール
10種混合ワクチンの接種スケジュールは、一般的に以下のようになります。
子犬の場合
生後6~8週齢で1回目の接種
生後10~12週齢で2回目の接種
生後14~16週齢で3回目の接種
成犬の場合
初年度は3回の接種
2年目以降は年1回の追加接種
ただし、愛犬の年齢や健康状態によってスケジュールが異なる場合もありますので、必ず獣医さんと相談してください。
10種混合ワクチンの費用は?
10種混合ワクチンの費用は、動物病院によって異なりますが、一般的には5,000円~8,000円程度です。
10種混合ワクチンの接種時の注意点
10種混合ワクチンを接種する際は、以下の点に注意しましょう。
接種前の健康チェック: 接種前に獣医さんに愛犬の健康状態をチェックしてもらいましょう。
接種後の経過観察: 接種後、愛犬の様子を注意深く観察し、異常があればすぐに獣医さんに連絡しましょう。
副反応: ワクチン接種後に、発熱、食欲不振、元気がなくなるなどの副反応が現れることがあります。これらの症状は通常、数日で治まりますが、心配な場合は獣医さんに相談しましょう。
狂犬病予防法について
狂犬病予防法により、飼い主には、生後91日以上の犬に年1回の狂犬病ワクチン接種を受けさせることが義務付けられています。
まとめ
この記事では、犬の10種混合ワクチンについて、飼い主さんが知っておくべき基本的な情報をまとめました。ワクチン接種は、愛犬の健康を守るだけでなく、飼い主さん自身の安心にもつながります。
この記事でご紹介した情報を参考に、獣医さんと相談しながら、愛犬に最適なワクチン接種計画を立ててください。
免責事項:
この記事は、一般的な情報提供を目的としており、獣医学的なアドバイスではありません。愛犬の健康に関する具体的な相談は、必ず獣医にご相談ください。