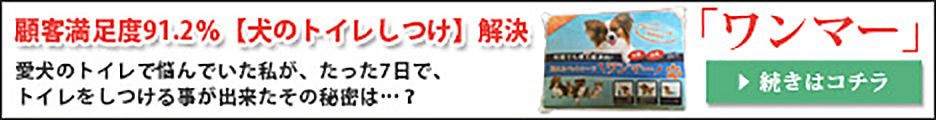見逃さないで!愛犬のSOSサイン:早期発見で守る、犬の健康
- えふ子
- 2024年7月31日
- 読了時間: 9分
愛犬がいつもと違う様子を見せた時、それは病気のサインかもしれません。犬は言葉を話せないので、体調の変化を飼い主さんがいち早く察知し、適切な対応をすることが大切です。特に、大病につながる可能性のあるサインを見逃さないように、注意深く観察しましょう。
この記事では、犬のよくある病気のサインとその対処法、早期発見の重要性について詳しく解説します。愛犬の健康を守るために、ぜひ参考にしてください。
目次
早期発見が大切な理由
よくある病気のサイン
食欲不振・嘔吐・下痢
元気がない・lethargy(無気力)
咳・くしゃみ・鼻水
皮膚のかゆみ・発疹・脱毛
歩き方・姿勢の変化
頻尿・血尿
目ヤニ・涙・目の充血
その他(体重減少、飲水量の増加、口臭など)
特に注意が必要な病気のサイン
病気のサインを見つけた時の対処法
定期的な健康チェックの重要性
まとめ
1. 早期発見が大切な理由
犬の病気は、早期発見・早期治療が重要です。症状が軽いうちに治療を開始することで、治癒率が高まり、愛犬の負担も軽減できます。また、早期発見によって、病気の進行を遅らせたり、合併症を防いだりすることも可能です。
特に、がんや心臓病、腎臓病などの大病は、早期発見が予後を大きく左右します。愛犬の健康を守るために、日頃から注意深く観察し、少しでも気になる症状があれば、早めに獣医に相談しましょう。
2. よくある病気のサイン
犬の病気のサインは様々ですが、ここでは特に注意が必要な、大病につながる可能性のあるサインを中心に紹介します。
食欲不振・嘔吐・下痢
食欲不振: いつも喜んで食べるフードを残したり、全く食べなくなったりする場合は、注意が必要です。食欲不振は、様々な病気の初期症状として現れることがあります。例えば、感染症、内臓疾患、歯周病、ストレスなどが原因で食欲不振になることがあります。
嘔吐: 吐くものが黄色い液体や白い泡の場合は、空腹時や胃酸過多が原因であることが多いですが、頻繁に吐いたり、吐くものが血や異物である場合は、すぐに獣医に相談しましょう。嘔吐は、胃腸炎、異物誤飲、中毒、膵炎などのサインである可能性があります。
下痢: ストレスや食あたりなど、一時的な原因で下痢になることもありますが、血便や粘液便、悪臭を伴う下痢が続く場合は、感染症や炎症性腸疾患などの可能性があります。寄生虫感染や腫瘍が原因で下痢になることもあります。
元気がない・無気力
元気がない: いつもは活発な愛犬が、急に元気がなくなり、寝てばかりいる場合は、注意が必要です。感染症や貧血、内臓疾患、ホルモン異常などが原因で、元気がなくなることがあります。
無気力: 無気力とは、反応が鈍くなり、何もする気が起きない状態を指します。これは、重篤な病気のサインである可能性があります。例えば、脱水症状、低血糖、高カルシウム血症などが原因で無気力になることがあります。
咳・くしゃみ・鼻水
咳: ケンネルコフなどの感染症や、心臓病、気管虚脱、肺がん、気管支炎などが原因で咳が出ることがあります。乾いた咳、湿った咳、吐き気などを伴う咳など、咳の種類によって原因が異なります。咳が続く場合は、早めに獣医に相談しましょう。
くしゃみ: アレルギーや異物混入、鼻腔内の腫瘍などが原因でくしゃみが出ることがあります。頻繁にくしゃみをしたり、鼻血を伴う場合は、注意が必要です。アレルギーの場合は、原因物質を特定し、除去することが重要です。
鼻水: 感染症やアレルギーなどが原因で鼻水が出ることがあります。透明な鼻水、膿のような鼻水、血が混じった鼻水など、鼻水の種類によって原因が異なります。鼻水が続く場合は、獣医に相談しましょう。
皮膚のかゆみ・発疹・脱毛
かゆみ: ノミやダニなどの寄生虫、アレルギー、皮膚炎などが原因でかゆみが出ることがあります。掻きすぎて皮膚が赤くなったり、出血したりする場合は、注意が必要です。かゆみの原因を特定し、適切な治療を行うことが大切です。
発疹: アレルギーや感染症、自己免疫疾患などが原因で、皮膚に発疹が現れることがあります。発疹の形や色、広がり方などによって、原因が異なります。発疹がひどい場合は、獣医に相談しましょう。
脱毛: ホルモン異常やアレルギー、皮膚疾患、栄養不足などが原因で脱毛が起こることがあります。一部分だけ脱毛する、全身の毛が薄くなる、脱毛部分の皮膚が赤くなるなどの症状が見られることがあります。脱毛の原因を特定し、適切な治療を行うことが重要です。
歩き方・姿勢の変化
歩き方: 足を引きずる、ふらつく、よろけるなどの歩き方の変化は、関節疾患(変形性関節症、膝蓋骨脱臼など)や神経疾患(椎間板ヘルニア、脊髄腫瘍など)、内臓疾患などが原因である可能性があります。
姿勢: 腰が曲がっている、背中を丸めているなどの姿勢の変化は、椎間板ヘルニアや脊椎腫瘍、腹痛などのサインである可能性があります。
頻尿・血尿
頻尿: 膀胱炎や尿路結石、糖尿病、子宮蓄膿症などが原因で、尿の回数が増えることがあります。頻尿は、痛みを伴う場合や、排尿困難を伴う場合があります。
血尿: 膀胱炎や尿路結石、腎臓病、腫瘍などが原因で、尿に血が混じることがあります。血尿は、重篤な病気のサインである可能性があるので、すぐに獣医に相談しましょう。
目ヤニ・涙・目の充血
目ヤニ: 目ヤニは、細菌やウイルス感染、アレルギー、異物混入などが原因で増えることがあります。黄色や緑色の目ヤニが出る場合は、感染症の可能性があります。目ヤニが多い場合は、獣医に相談しましょう。
涙: 涙が増えるのは、結膜炎や角膜炎、異物混入、緑内障などが原因である可能性があります。涙が多い場合は、目をこすったり、痛がったりする様子が見られることもあります。
目の充血: 結膜炎や角膜炎、緑内障、ぶどう膜炎などが原因で、目が充血することがあります。充血がひどい場合や、痛みを伴う場合は、すぐに獣医に相談しましょう。
その他(体重減少、飲水量の増加、口臭など)
体重減少: がんや内臓疾患、糖尿病、寄生虫感染などが原因で、体重が減少することがあります。急激な体重減少は、特に注意が必要です。
飲水量の増加: 糖尿病や腎臓病、子宮蓄膿症などが原因で、飲水量が増えることがあります。飲水量が増えるだけでなく、尿の量や回数も増える場合は、注意が必要です。
口臭: 歯周病や内臓疾患などが原因で、口臭が強くなることがあります。歯周病は、歯肉炎や歯槽膿漏など、歯や歯ぐきの病気の総称です。内臓疾患の場合は、口臭だけでなく、嘔吐や下痢などの症状を伴うこともあります。
3. 特に注意が必要な病気のサイン
犬の病気のサインは多岐にわたりますが、中には特に注意が必要なサインがあります。これらのサインが見られた場合は、愛犬の命に関わる可能性もあるため、一刻も早く動物病院に連れて行きましょう。
意識消失、痙攣: 脳腫瘍、てんかん、低血糖、熱中症などが考えられます。意識消失は、呼びかけても反応がない状態です。痙攣は、体が硬直したり、手足が不随意に動いたりする状態です。これらの症状は、脳に異常があることを示している可能性があります。
呼吸困難: 心臓病、肺水腫、気胸などが考えられます。呼吸が速い、浅い、苦しそうにしている、口を開けて呼吸するなどの症状が見られます。呼吸困難は、酸素不足に陥っている状態であり、放置すると命に関わる危険があります。
ぐったりしている: 感染症、脱水症状、内臓疾患などが考えられます。ぐったりしている状態は、元気がなく、反応が鈍い状態です。重篤な病気の場合は、意識レベルが低下することもあります。
異物を飲み込んだ: 腸閉塞、中毒などが考えられます。異物を飲み込んだ場合は、嘔吐、下痢、食欲不振などの症状が現れることがあります。
異物が腸に詰まってしまうと、腸閉塞を起こし、開腹手術が必要になることもあります。
急に歩けなくなった: 椎間板ヘルニア、骨折、関節炎、神経疾患などが考えられます。急に歩けなくなる場合は、痛みを伴うことが多く、犬は鳴いたり、足を触られるのを嫌がったりします。椎間板ヘルニアは、背骨の間にある椎間板が変形し、神経を圧迫する病気で、早期の治療が必要です。
出血が止まらない: 血液凝固異常、外傷などが考えられます。出血が大量だったり、長時間止まらなかったりする場合は、すぐに獣医に診てもらいましょう。
これらのサインに加えて、以下のような症状も注意が必要です。
高熱: 感染症や炎症、熱中症などが考えられます。犬の平熱は38.0〜39.0℃程度ですが、これよりも高い場合は、すぐに獣医に相談しましょう。
体重の急激な減少: がんや内臓疾患、糖尿病、寄生虫感染などが考えられます。短期間で体重が5%以上減少した場合は、注意が必要です。
多飲多尿: 糖尿病や腎臓病、子宮蓄膿症などが考えられます。いつもより水をたくさん飲むようになったり、尿の量や回数が増えたりした場合は、注意が必要です。
黄疸: 肝臓病や胆嚢疾患、溶血性貧血などが考えられます。白目や歯茎が黄色くなるのが特徴です。黄疸は、肝臓の機能が低下しているサインである可能性があります。
呼吸時の異音: 心臓病や呼吸器疾患などが考えられます。ゼーゼー、ヒューヒュー、ゴロゴロといった異音が聞こえる場合は、注意が必要です。
4. 病気のサインを見つけた時の対処法
愛犬に病気のサインが見られた場合は、以下の手順で対処しましょう。
落ち着いて観察する: いつから症状が出ているのか、どのような症状があるのか、詳しく観察しましょう。症状が悪化していないか、他の症状が出ていないかなど、注意深く観察することが大切です。
記録する: 症状や変化を記録しておくと、獣医に伝える際に役立ちます。いつから症状が始まったのか、症状の頻度や程度、愛犬の食欲や元気など、できるだけ詳しく記録しておきましょう。
早めに獣医に相談する: 自己判断で治療せず、必ず獣医に相談しましょう。インターネットや書籍で得た情報だけで判断せず、専門家の意見を聞くことが大切です。
獣医に相談する際は、以下の情報を伝えられるように準備しておきましょう。
症状が出ている期間
症状の種類
愛犬の年齢、性別、犬種
過去の病気やケガ
現在服用している薬
ワクチン接種状況
食生活や生活環境
これらの情報を伝えることで、獣医はより正確な診断を行うことができます。
5. 定期的な健康チェックの重要性
定期的な健康チェックは、病気の早期発見に繋がります。若いうちは年に1回、7歳以上になったら年に2回、動物病院で健康診断を受けましょう。
健康診断では、身体検査、血液検査、尿検査、糞便検査などを行います。これらの検査によって、目に見えない病気のサインを発見することができます。
また、ワクチン接種やフィラリア予防も、定期的に行いましょう。ワクチンは、感染症を予防するための有効な手段です。フィラリアは、蚊を媒介とする寄生虫で、心臓に寄生すると命に関わる危険があります。
6. まとめ
愛犬の健康を守るためには、飼い主さんが病気のサインにいち早く気づくことが大切です。この記事で紹介したサインを参考に、愛犬の体調を日頃から注意深く観察し、気になることがあれば、早めに獣医に相談しましょう。
早期発見・早期治療によって、愛犬の健康を守り、楽しい生活を長く続けられるようにしましょう。